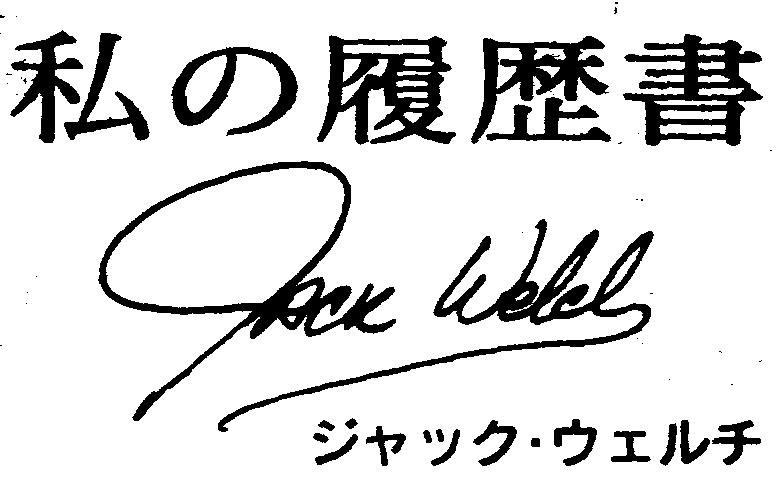
日本経済新聞 2001/10
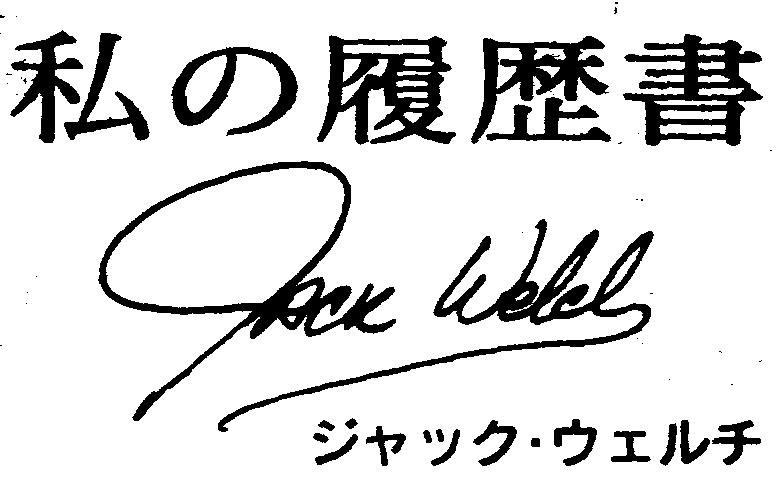
GEとの別れ 理想の会社から引退 自伝発売の日にテロ事件
先月の7日にGE(ゼネラル・エレクトリック)会長を退職した。米国を代表する総合電機メーカーのCEO(最高経営責任者)の地位に就いたのが1981年春、GE史上最年少の45歳だった。それから丸20年、ひたすらこの会社を世界で最良、最高の会社に育てることに専念してきた。その結果、世界で最も優れた人材を生む「人間工場」「境界のない教育文化機関」を創造することができたと確信している。
引退前夜の9月6日夕、ニューヨーク郊外のクロトンビルにあるGE経営開発センターで送別会があった。敷地52エーカー(約21万平方メートル)、緑に囲まれたセンターは、私が会長就任以来、幹部社員に会社のビジョンを説いてきた場所だ。どの部門もその業界で1位か2位でなければ思い切って撤退しよう、大企業にはびこる官僚主義を打破しよう、と訴えてきた。ここで「シックス・シグマ」「ワークアウト」など大胆な経営合理化プログラムを開発し、実践してきた。その結果、ここはGEの最も重要な工場ー熱く学び、鍛える「人間工場」となった。
私はここで21年間に1万8千人近い経営幹部と直接対話した。ここに来ると私はいつも若返った。会長の仕事のうちでも最高に楽しい時間だった。
それだけに私の引退を記念するのに最もふさわしい場所だ。パーティーには、幼友達からGEの仲間たち、ジェフ・イメルト新会長まで、約200人が集まった。堅苦しいあいさつ、セレモニーは一切なし。そんなものこそ私が最も嫌い、GEから追放したことを全員がよく知っている。だからスピーチも私の失敗談、裏話など、私を笑い飛ばそうというものばかり。大した役者ぞろいで、私は文字通り「ロースト」(あぶり焼き)され、爆笑の連続だった。 センターはこの日「ジョン・F・ウェルチ・リーダーシップ開発センター」と改名された。
9月11日、私はニューヨーク市内にいた。ちょうどこの日、私の自伝が発売され、全米各地の出版記念ツアーを始めることになっていた。午前7時半、NBCテレビに出演し、続いてCNBCの衛星中継インタビューを受けるため、新しいスタジオに入った時だった。モニターテレビで世界貿易センターとペンタゴンが襲撃されるのを見た。超高層ビルが崩壊するのをくぎ付けになって見つめていた。
われわれは大変な衝撃を受け、恐ろしさにぞっとした。続いて苦痛と、テロに対する怒りが猛然と込み上げてきた。都市を破壊し、残酷に数千人もの命を奪い、残された家族を悲嘆にくれさせる犯行は許せない。
それから2週間余り、私は無慈悲に奪われた命に涙する一方、消防士や警察官らの英雄的な救出活動に誇らしさで胸がいっぱいになっている。アメリカがこれほど一致団結したことはなかったろう。テロの暴力に対して、われわれは声をそろえて反対している。大統領も果敢にリーダーシップを発揮し、国民全体が彼を支持している。こうした誇りと団結心が惨事からの苦痛をいやしてくれている。
GEでの41年間、浮き沈みがたくさんあった。マスコミには褒めそやされたり、たたかれたりの連続だった。だが、私自身は本質的には東海岸の港町の少年時代からほとんど変わっていない。
この「履歴書」は、企業人向きでない男が大企業の中であちこちつまずきながらも前進し続け、生き残り、ついに栄光を手に入れる幸運な物語だ。と同時に、私の周りにいた何千人もの優れた人たちが挑戦し成し遂げた成功物語でもある。彼らのおかげで私の旅路が実り豊かなものになったのだから。
生い立ち 愛に満ちた母の教え 鉄道員の父、仕事に誇り
私が生涯で最も大きな影響を受けた人物といえば、それはわが母、グレース・ウェルチだ。競争することに価値があること、勝つ喜びと同時に、負けを潔く受け止めることを教えてくれたのは母だった。もし私に指導者としての資質があり、周りの人から最善のものを引き出す方法を身につけているとしたら、それは母から授かったものだ。常に現実を直視することをたたき込んでくれたのも母だ。「勉強しなければ、絶対に立派な人間になれないわよ。うまい近道などないの。自分をごまかしてはダメ」が母の口癖だった。
私と母との関係はきわめて強力で、ユニークで、暖かくて、豊かに広がっていくものだった。母は私が最も心を許して信頼できる人であり、最良の友だった。私が高齢出産で授かった一人っ子だったせいかもしれない。私が生まれたのは1935年11月19日、マサチューセッツ州ピーボディの町で、母が36歳、父が41歳の時だった。それまでずっと何年も子供が欲しいと願っていて、それがようやくかなったわけだ。それだけに母は私を長年探し求めていた宝物のように扱い、惜しみなく愛情を注ぎ込んでくれた。
私は、銀のスプーンを口にくわえて生まれるような裕福な家庭に恵まれたわけではない。だがもっといいもの、つまり量り切れないほどの大きな愛情に恵まれた。
私の両親の親たちは、どちらもアイルランドからの移民で祖父母も両親も、だれ一人として高校まで卒業していなかった。私が9歳の時、両親は初めて家を買った。州の中心市、ボストンから20キロほど北の小さな町、セーラムで、アイルランド移民の労働者が居住していた地区にあるちっぽけな石造りの二階建ての家だった。
わが家の前には通りを挟んで小さな工場があった。父はよく、それが実にいい、と言っていた。「近所に工場があるのはいいものだ。週末は休みで静かだから、邪魔にならない」。私は素直にそれを信じていた。父がそんな言葉で自分に自信を持とうとしていたことに気づきもしなかった。
父はボストン&メーン鉄道の通勤電車区の車掌だった。毎朝5時に出勤する時には、母がアイロンをかけた濃紺の制服と、パリッと糊(のり)のきいた白いワイシャツに身を包んで、父はまるでこれから神に敬礼するような雰囲気だった。ほぼ毎日、同じ手順で、切符にハサミを入れながら、ボストンからニューペリーポートまでセーラムを挟んで10駅、約60キロの区間を何度も往復していた。
父は毎日、まるで自分が所有している専用車のように楽しそうに列車に乗り込み、車内を悠然と歩き、顔見知りの乗客には親友のように親しげにあいさつして回っていた。車内ではいつも快活に、ユーモアたっぷりにおしゃべりしていたが、わが家に戻ると、態度が一変して、もの静かで、引っ込み思案だった。そこで母がよく「家でも少し愛想よくしたらどうなの」とこぼしたが、めったにそうなることはなかった。
父は勤勉で、長時間働いて、一度も遅刻したことがなかった。天気予報が悪いと、前夜のうちから母に車で駅まで送らせ、列車内に寝て、翌朝の勤務に備えていた。夜は7時前に帰宅することはめつたになく、客の残した新聞の束を抱えて持ち帰った。私も6歳のころから毎晩、たくさんの新聞を読むようになり、それ以来今日まで、ニュース中毒になっている。
母のしつけ 自負心が最高の財産ハンディあっても前向き
小学校に通うころには、母が人より秀でなければならないことを教えてくれた。母はいつ、どんな風に私に厳しく接したらいいか、いつ優しく抱いてキスするのがいいかをよく心得ていた。自分がどんなに母に期待され、愛されているかを常によくわからせてくれた。成績表でAが4つ、Bが1つだと、母はなぜBがついているのか問いただしたが、最後には決まって「よくたくさんAがとれたね」と抱きしめてくれた。
母は私がちゃんと宿題をやっているかどうかをチェックしていて、そのやり方は今日、私が仕事の進捗(ちょく)状況をチェックするのに見習っているものだった。二階の自分の部屋で宿題などそっちのけでいると、一階の居間から「まだ終わらないのね。宿題が済むまで下りてきちゃあダメよ」という声がよく聞こえてきたものだった。
私が何よりも競争することの面白さ、喜びを学んだのは、台所のテーブルで母とよく「ジン・ラミー」というカードゲームをして遊んだことからだった。小学一年生のころは、学校から昼ご飯を食べに戻るのに、母とカードゲームをしたい一心で飛んで帰ったものだ。そして母がしょっちゅう勝って、最後の勝ち札を置きながら「ジン」と大きな声を出すたびに、私は悔しくてカッとなり、今度こそ勝とう、明日こそ勝とう、と思ったものだった。
これがおそらく私の競争心の起点であり、その後の野球、ホッケー、ゴルフ、そしてビジネスヘとつながっていったものだろう。
母が私にくれた最高の贈り物をたったひとつだけ挙げるとすると、それは多分、自負心だろう。自分を信じ、やればできるという気概を持つことこそ、私が自分の人生で一貫して求め続けてきたことであり、私と一緒に働く経営幹部一人ひとりに育(はぐく)んでほしいと願ってきたことだ。自負心があれば、勇気が生まれ、遠くまで手が伸びる。自分に自信を持つことでより大きなリスクも負えるし、最初に自分で思っていたよりもはるかに多くのことを達成できるものだ。
母は人事管理の仕事をしたことなど一度もなかった。だが、自尊心を育てるにはどうすればいいかを実によく知っていた。私には幼い時から言語障害があって、吃(ども)る癖がなかなかとれなかった。そのせいでマンガチックなことが時々起きた。カトリック教徒は昔は金曜日には肉を食べない習慣を守っていた。そこで大学生になっても食堂で「ツナ・サンドイッチ」を注文するのに「ツ、ツナ」と吃ってしまい、2個出されることがよくあった。母は私が吃るのに最高の口実を教えてくれた。「お前は頭がすごくいいから吃るんだよ。お前の頭の回転の速さに追いつく舌など誰も持っていないよ」。それを素直に信じていて、吃りを気にすることもなかった。
母が幼い私にどれだけ自信を植え付けてくれたか、に気づいたのは大人になってからだった。小学生の時のバスケットボール・チームの写真を見ると、私は他の選手に比べて4分の3くらいしか背丈がない。小中学生時代の他のどのスポーツ・チームの写真を見ても、私は常に最も背が低くて小柄だった。
今なら「何てチビだったんだ」と笑ってしまうが、当時は不思議なほど、自分がそんなチビだということを全く考えもしなかったし、感じたこともなかった。それも母がいつも「人は自分が望むような人間になれる」「あとは自分の心がけ次第よ。何事も思い切って一生懸命やるだけ」と言い聞かせてくれていたからだろう。母の家系は皆、心臓病で亡くなっていた。それで母も若死にする不安をよく口にしていた。その分余計に、一人息子が早くから独立心を育むよう心掛けてくれたのだった。
セーラムの町 運動から競争心学ぶ 「負け方悪い」と母に大目玉
セーラムは子供が育つには素晴らしい町だった。勤勉な労働倫理と優れた価値観が支配していて、当時は家にカギをかける人など一人もいなかった。土曜日には子供たちは25セント貨を1枚握って映画館に行き、ポップコーンを1箱抱えて二本立ての映画を見て、帰る途中でアイスクリームを買って食べられたから、親は何も心配することもなかった。日曜日には、どこの教会も信者でいっぱいだった。セーラムの子供たちは毎年夏、専用列車で隣のメーン州の海浜遊園地まで遠足に行くのが最大の楽しみだった。朝6時半に乗り、2時間後に到着。そこで1、2時間もいろんな乗り物に乗ると、手持ちの5ドルほどの小遣いは使い果たしてしまう。まだ半日もあるのにもう破産状態だ。そこで友達と浜辺を巡っては、空きビン拾いをして回った。1ビン2セントで引き取ってもらい、それでホットドッグを買い、また乗り物に乗れた。
セーラムは雑多なものがいっぱいあって、競争心に満ちた町でもあった。私も競争するのが大好きだったし、友達もみんなそうだった。次から次へといろんなスポーツを楽しんだ。隣組同士で野球、バスケットボール、フットボール、ホッケーのチームをつくっては、大通りから離れた裏のほこりっぽい空き地でゲームした。春から夏にかけては地ならしをして敵味方に分かれてチームを編成し、トーナメント方式で日程表までつくって対戦した。朝早くから、町の警笛が午後8時45分に鳴るまでゲームしていた。この警笛が子供の帰宅時間になっていた。
町が学校区で分かれていたから、小学校レベルでもあらゆるスポーツで競い合った。私は小学校の6人制フットボール・チームのクォーターバックだった。足は遅かったが腕力があった。仲間に2人、素晴らしい俊足の選手がいて、地区大会で優勝した。私は野球チームの投手もやって、大きく曲がるカーブと鋭く落ちるドロップを覚えた。
ただ、セーラム高校に進学して、私はフットボールでも野球でも、自分のピークが過ぎたことを発見した。フットボール選手としては走るのが遅すぎたし、12歳の時に素晴らしかったカーブもドロップも、16歳になると通用しなくなっていた。私の速球がファウルされて窓ガラスを割ることもなくなった。打者は座って待っていてもいいくらいになっていた。高校1年の時には先発投手だったが、3年の時にはベンチにいた。幸いホッケーでは高校でも主将で最多得点を出す選手だったが、大学に入ると、スピードのなさが難点で、選手を続けることを断念せざるを得なかった。
あれは高校3年の最後のホッケー・シーズンの時だった。わが「セーラム・ウイッチズ(セーラムの魔女)」は3勝のあと6連敗で、最後の宿敵、ビバリ一高との試合には何としても勝ちたかった。白熱したいい試合で、主将の私が2点ゴールを挙げ、2対2の延長戦に入ったが、すぐに得点を許し、7連敗を喫してしまった。悔しさのあまり、私は氷上にスティックを放り投げて、控室に戻った。
選手みんなで着替え始めたところに突然、ドアが開いて、母が入ってきた。花柄の服を着た母はわき目も振らず、いきなり私のユニホームの胸ぐらをつかみ、顔を近づけて叫んだ。「このボケナス!負け方も知らない者が勝てるわけがない。負けてみっともないマネをするくらいなら、試合に出るんじゃないッ」。みんなの前で恥をかいたが、その時、母に言われたことは、今でも鮮明に心に残っている。
母の仕置き わんぱく時代の「学習」 人を見る目、自然に教わる
子供時代の私は、ものをねだったり、駄々をこねたりすることはなかったが、両親は私のためにずいぶん無理をしてくれた。いい野球グローブや高級自転車を買ってくれた。父は母が私を甘やかすのを許し、何事もお母さんのおかげ、と思わせてくれていた。
母は私をボストン・レッドソックスの野球場に連れて行って、外野席からテッド・ウイリアムズ選手が外野を守っているのを間近に見せてくれた。敬けんなカトリック教徒だった母は、朝6時からの教会ミサで私が戒壇の世話ができるよう車で送り迎えし、いつも決まって右側最前列に座ってお祈りをしていた。 母は我が家の戒律を守る役をずっと務めていた。私が友達と一緒に学校をさぼってボストンまでお祭りで遊びに行った時のことだ。帰りの列車で1本50セントの安物ワインをみんなで飲んでいたのを父に見つかったが、父は友達の手前、何も言わず、帰宅してから母に話した。当然、母にはたっぷりと説教され、厳しい刑罰を執行された。
また、ある1月の寒い朝、教会の戒壇係を逃れて、自宅近くの凍った池で友達とホッケーのゲームをしていて、氷の割れ目に落ち、ずぶぬれになったことがあった。急いで衣服を脱ぎ、ガタガタ震えながら、たき火のそばの木につるして乾くのを待った。これで何とかごまかせる、と思いながら家の玄関の月を開けて入ったとたん、ほんの1秒で母が「服が煙臭い」ととがめた。戒壇係をさぼるというのは、自宅の壁に十字架を飾り、ロザリオをもみながらお祈りし、教会の神父を聖者と考えている人間にとっては、許しがたいことだった。母は私をその場に座らせ、罪を告白させ、その上でお仕置きをした。私から脱がせたばかりのぬれた靴を手にすると、思いつきり強くたたいたのだ。
母は厳格ではあったが、同時にとても「甘く優しい母」にもなった。私がまだ11歳にもならないころだったが、町にやって来た移動遊園地のゲーム場からボールを1個盗んだことがあった。射的台に並んだミルク缶に当てて落とすと、キューピー人形がもらえるというゲームで使うボールだ。ほどなく母に見つかり、どこで手に入れたか、聞かれた。盗んだことを認めると、母は神父さまの所に返しに行き、臓悔(ざんげ)してきなさい、と言う。教会の司祭たちはみんな私のことを知っているから、懺悔室に入って一言口をきいただけで、すぐに私だとわかってしまうのは確実だった。そんなことはとても怖くてできない。
私はボールを運河に捨てることで勘弁してほしいと頼んだ。交渉の末、母は私のやり方を認め、車で運河にかかる橋まで行き、私がボールを川に投げ捨てるのを見届けた。
タフで精力的で、しかも暖かくて寛大でーー母は人の人間性を見抜く偉大な判事でもあった。会った人については必ず人格を判断できたし、「うさん臭い人は1マイル先からでもわかる」と言っていた。 母は極端なくらい、友達には思いやりが深くて親切だった。もし親せきか近所のだれかが訪ねてきて、食器棚のグラスがすてきだとでも言ったら、まずためらうことなく、よかったら差し上げるわ、と言ってきかない人だった。
その半面、もし母とぶつかったら、気を付けたがいい。自分の信頼を裏切る人に対しては、決して容赦はしないから。そして、こうした性格はそのまま、私自身が母から受け継いでいるものだと言える。
アルバイト ゴルフ場でキャディー
ゲームとマナーを覚える
子供時代の最も強烈な思い出として、母が泣いているのを見たことが挙げられる。1945年4月のことだ。私はまだ9歳で、それまで母の泣き声を聞いたことなど一度もなかった。母は台所で父のシャツにアイロンをかけながら、顔中いっぱいに涙をこぼしていた。「おお、神様、フランクリン・ルーズベルトが亡くなるなんて」
私はただビックリしていた。大統領の死がどうしてこんなに母の心を傷つけるのか、わからなかった。私が母と同じような気持ちになったのはその18年後、ケネディ大統領が暗殺された時であり、私もテレビにくぎ付けになって悲報に泣いた。
母がルーズベルトの死をそんなに悼んだのは、大統領がわが国を救い、民主主義を救ったと心から信じていたからだった。大統領と政府を深く信頼していた。父もそうだ。二人とも、政府が国民の意思を尊重し、市民を守り、常に正しいことをしていると信じていた。私もまた長い間、両親にならって政府を信頼していたが、のちには、その信頼感が何度も厳しく問われることが起きていった。
父は私に町の外で何が起きているかを教えてくれ、同時にまじめに働くことがいかに大切かを、身をもって示してくれた。さらに私が一生、楽しめるものも教えてくれた。ゴルフだ。父は「列車の乗客の中でも大物になる人はいつもゴルフ談議している」と言い、野球やホッケーよりもゴルフを覚えたほうがいいと考えていた。近所の年上の子供たちはゴルフ場でキャディーをしていた。私は父の勧めで他の子よりも早く、9歳の時からキャディーをやり始めた。
週日は母が午後早い時間に学校まで私を迎えに来て、車で3,4キロ離れたゴルフ場まで連れて行ってくれた。それで他のキャディーの子よりも早く仕事の順番が回ってきた。土曜の朝には仲間と墓地の入り口に座って、通りがかりのゴルフクラブのメンバーの車に乗せてもらって通勤した。18ホールを回ってキャディー賃は1.5ドル。当時、チップをくれる客はほとんどいなかったから、仲間はみんな、チップを弾む客のバッグを持つ番に当たりたがった。
私たちは月曜の朝もゴルフ場に行った。午前中は職員がコースを整備することになっていたので、私たちはロストボールを拾って回ったり、自分たちで18ホールのゲームをしたりした。正午きっかりには追い出されるので、夜明けとともに通ったものだった。
キャディーをやって、お金をもらえたが、それよりも重要なのはゲームを覚えたことだ。それと、社会的にある程度成功した人たちに身近に接することができたことだ。彼らがコースでどんな振る舞いをするかを見ていて、人がどんなに魅力的になるか、あるいはとんでもない下品な人間になるかを学ぶことができた。
中学、高校時代、キャディー以外にも実にいろんな仕事をした。しばらく新聞配達もしたし、長期休暇の時には郵便局で働いた。町の繁華街の靴屋と契約して、1足売るごとに7セントの歩合をもらう仕事も3年ほどやった。歩合のいい派手な高級靴を売るのに、臭い足に履かせては「実によく似合いますよ」と調子のいいお世辞を言うことも覚えた。
ある夏、町のゲーム機械工場で小さなコルクに旋盤で穴をあける作業をやったが、毎日ペダルを踏んで全く同じものを何千個もつくるのに頭が痛くなり、ほとほと嫌になって、3週間と持たなかった。それで自分のやりたくない仕事が何かを十分に学んだ。
高校3年になって、ゴルフクラブの会員の中でも最もケチの部類にいた男のキャディーをした時のことだ。もうキャディー歴8年で、ちょっと長くやりすぎていたせいかもしれない。第6ホールで、池を越えてティーまで100ヤードほどの地点から、男がボールを池に直接打ち込んでしまった。泥池で岸から3メートル以上離れた所に落ちたが、私に「靴も靴下も脱いで、ボールを取ってこい」と言う。私が拒否すると、どうしても取れ、と言い張る。私もカッとなって悪態をつき、男のクラブを何本かつかんで池に放り投げ、「クラブもボールも全部自分で取りに行け」と言って逃げ帰った。
それは同じ年にホッケーの負け試合で頭に来てスティックを投げ捨てたことよりも愚かな行為だった。この事件のせいで、キャディーでもらえた奨学金をフイにしてしまって、母をガッカリさせたが、母はその時の私の気持ちを理解してくれたためか、それほど厳しいお仕置きはなかった。
母をもっと失望させたのは、海軍の奨学制度で四年制大学に無償で進学できる機会を逸したことだった。セーラム高校からは私を含めて3人が試験に通り、父が州議会議員に推薦状を書いてもらい、何段階もの面接試験も何とかこなした。2人の親友は無事にパスして、1人はタフツ大に、もう1人はコロンビア大に入った。私はダートマス大かコロンビア大を志望していたが、最終的に奨学金は支給されなかった。失格の理由はいまだにわからない。
皮肉にも、奨学金をもらえなかったことで素晴らしい農会に恵まれることになった。高校ではいい成績を取るために一生懸命勉強したが、だれも私をすごい天才、秀才とは思わない。そこで私は州立のマサチューセッツ大アマースト校に願書を出した。授業料が半年間でわずか50ドル、寄宿舎の寮費など全部含めても1000ドル以下で卒業できるからだった。
親戚中でも私のほかに大学に進学したのは従兄弟(いとこ)が1人いるだけで、進路を決める参考になりそうなのは、セーラムの発電所で技師をしている伯父くらいだった。技術者になる、というのがよさそうに思えて、早くから化学が好きだったので、化学工学科を専攻した。
大学についてはほとんど何も知らなかったので、もう少しで進学しそこなうところだった。海軍の試験だけで十分と思い込んでいて、進学適性テストも受けていなかった。大学から入学許可通知が来たのは1953年6月、高校の卒業式のわずか数日前だりた。私は補欠リストに入っていて、辞退者が出たので繰り上げ入学が認められたらしい。コロンビアやダートマスほど競争が激しくない大学に入ったのは、結果として、私にとって非常に有利だった。当時の学内の競争は楽なもので、私は苦労せずに輝くことができたからだ。
ただ、いくら自信満々といっても、秋からの新学期の最初の1週間はきつかった。それまでずっと家にいて、一度も外泊したことがなかったから、たちまちホームシックにかかってしまった。私の泣き言を聞いて、母が車で3時間かけてキャンパスに訪ねてきて、励ましてくれた。「周りの子たちを見てごらん。だれも家に帰りたいなんて思っていないよ。お前もあの子たちと同じだし、たぶんお前の方がもっと優れているんだよ」
たしかに、私は他の学生のように大学で過ごすことについて心の準備ができていなかった。初めての体験に気が動転していたのだ。東部の予備校から来た者、ボストンの名門進学校から来た者の中には私よりずっと数学ができる学生がいたし、物理学が相当むずかしいこともこたえていた。だが、母の言葉ですっかり落ち着き、翌週には不安もなくなっていた。